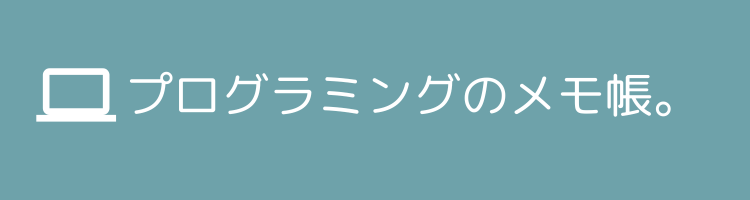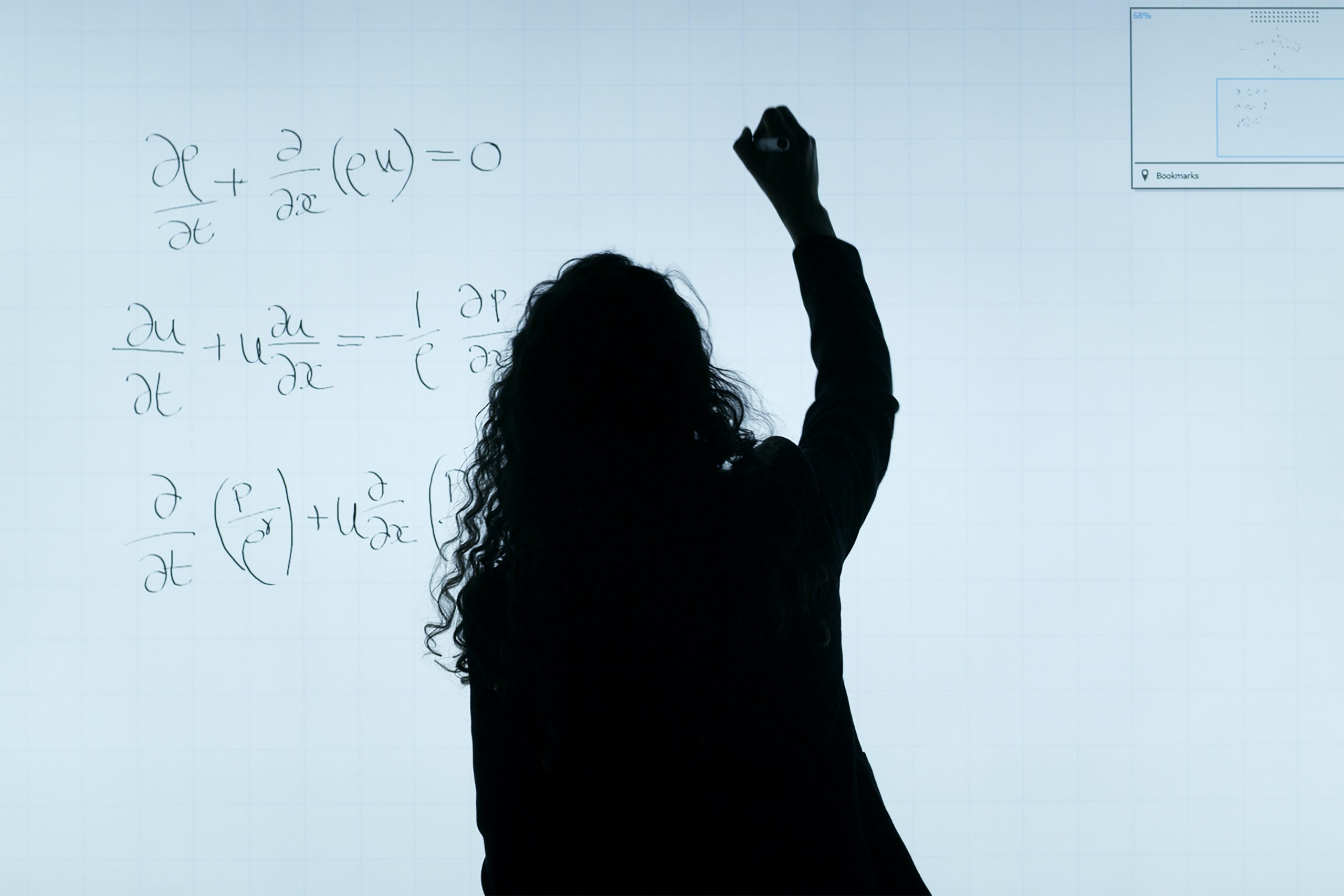部材が温度変化を受けると長さが変わります(熱膨張)。
本ページでは、熱膨張の基本式・材料別の線膨張係数の目安・誤差に関する注意点をまとめ、さらにその場で計算できるツールを用意しました。設計の当て勘や確認にお使いください。
熱膨張量の式
ΔL=α×L0×ΔT
ΔL:伸び量[mm]
L0:初期長さ
ΔT=T2−T1:温度差(℃)
α:線膨張係数[1/℃またはppm/℃]
線膨張係数の目安(室温付近)
| 材料 | 係数(ppm/℃) | 備考 |
|---|---|---|
| アルミニウム(Al) | 23 | 軽くてよく伸びる |
| 鉄/炭素鋼 | 12 | 構造材の目安 |
| ステンレス(SUS304) | 17.3 | 代表的オーステナイト系 |
| 銅(Cu) | 16.5 | 熱伝導率が高い |
| 黄銅(Brass) | 19 | 真鍮 |
| ガラス(ソーダ石灰) | 9 | 種類により差あり |
| コンクリート | 10 | 調合・水分で差あり |
ppm/℃ は「100万分の1/℃」。式に入れるときは 1/℃ に直して使う(ppm/℃ ÷ 1,000,000)。
プログラム
print("熱膨張量の計算*****ΔL=α(T2-T1)L*****")
L = input("L:熱膨張を計算したい方向の長さ[mm]=====>>")
T1 = input("T1:変化前の温度[℃]=====>>")
T2 = input("T2:変化後の温度[℃]=====>>")
a = input("α:線膨張係数[10^-6/℃]=====>>")
D_L = float(a)*(float(T2)-float(T1))*float(L) * 0.000001
print("ΔL:熱膨張量:",D_L,"[mm]")上記がプログラムになります。
それでは解説していきます。
L = input("L:熱膨張を計算したい方向の長さ[mm]=====>>")最初に、熱膨張を計算したい方向の長さ[mm]を入力するようにしています。
T1 = input("T1:変化前の温度[℃]=====>>")次に変化前の温度を入力するようにしています。
T2 = input("T2:変化後の温度[℃]=====>>")その次に変化後の温度を入力しています。
a = input("α:線膨張係数[10^-6/℃]=====>>")線膨張係数を入力しています。
D_L = float(a)*(float(T2)-float(T1))*float(L) * 0.000001ここで熱伸び計算を行っています。「0.000001」をかけているのはmm表示に直しているためです。
print("ΔL:熱膨張量:",D_L,"[mm]")最後に結果を出力しています。
その場で使える:熱膨張計算ツール
熱膨張(伸び量)計算ツール
ΔL = α × L₀ × ΔT(材料の係数は目安・ppm/℃入力可/単位は mm・cm・m)
結果
入力して「計算する」を押してください。
前提と注意点(クリックで開く)
- 室温付近の線形近似前提(α一定)。高温/極低温では温度依存に注意。
- 拘束条件・湿度・経年(クリープ)などで実機は変わります。重要設計は実測/カタログ値で再確認。
- ppm/℃入力は内部で
α = (ppm/℃) ÷ 1,000,000に換算します。
使うときの注意
- 室温付近の線形近似の範囲で使ってください。広範囲の温度ではαが温度依存します。
- 実機では固定端・熱伝達・湿度・経年などで誤差が出ます。重要設計は必ず実測・メーカー値で再確認を。
- 係数は目安です。正式値は材質規格・カタログを参照してください。